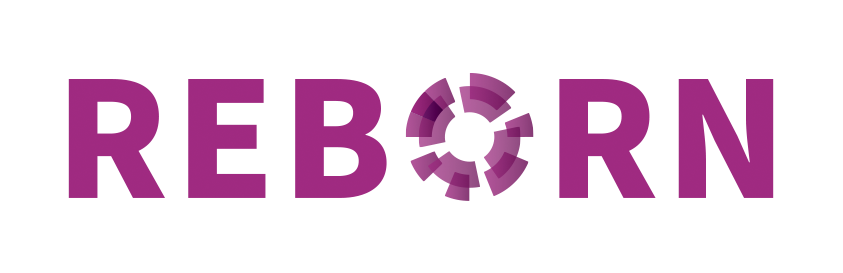店頭プロモーションに携わっている関係上、食品スーパーに行く機会が多いのですが、時に「こんなことをやっていて大丈夫かな?」というお店を見かけます。
毎日のように行われている値下げ(値引き)です。
来店者にとってはありがたいことだと思いますが、長い目で見た時に日常化している安易な値下げは経営にとってはとても危険な結果につながりかねないので気をつけたいところ。
ということで、今回は安易な値下げが食品スーパーの将来にどういう影響を及ぼすのか、それを打破するためには何が必要なのかを書いてみたいと思います。
(長くなるので何度かに分けて書きます。よろしければ読んでみてくださいね)
食品スーパーの安易な値下げ(値引き)による弊害: 商品が育たない

現在、食品スーパーは所狭しと競合が乱立し、生き残りをかけて切磋琢磨しています。
その中で自社の価値を上げるために企業努力によって「いいものをより安く」商品を提供しているのは素晴らしいことだと思います。
ただ、それでも来店数がなかなか増えなかったり、売れなくなってきたりすると目先の利益を求めてついつい安易に値下げ(値引き)に走ってしまう店舗は少なくありません。
でも、それを初めてしまうといろんな弊害が出てきます。
まず、一つは商品が育たなくなるということです。
食品スーパーの安易な値下げ(値引き)による弊害: 健全な利益を生めない魅力のない売場

バイヤーの方がいくら「いい商品だ」と思って仕入れても、「それがどういいのか?」「他社とどう違うのか?」「どんなメリットが得られるのか?」が売場で表現できていないとお客様は価値がわからないため買おうという気にはなりません。
品質の良さや隠れた潜在的なニーズを表現したり、試食販売などで体験をさせてあげたりして「買う理由」を明確にしない限り、いくらいい商品でもお客様に価値が伝わることはないんです。
ただでさえ、今はどこでも代替え商品や同品質の商品がゴロゴロあります。
そんな中どんなに優れた商品でも、大した販促活動もせず棚に並べているだけでヒット商品になることはありません。
単に並べているだけで「この商品は売れないな」と判断して終わるのでなく、食品メーカーの方とともに「いかにして価値に気づいてもらうか?」を考えて実践しないと、本来得るべき利益はいつまで経っても得ることはできません。
ちなみに販促(プロモーション)に力を入れずに、商品頼みになっていると売り筋商品だけがお店に残るようになります。
そうなると先に待っているのは、他店と何の差別化もできない平凡でつまらない売場。
当然、買い物の楽しみを感じられないことから次第に客離れが起き、来店するのは常に値下げ商品を待っているお客様だけになります。
また、食品メーカーからも「この店舗はウチの商品を育てる力がない」と判断され、徐々に疎遠になり、関係性も崩れてしまいます。
食品スーパーの安易な値下げ(値引き)による弊害:知恵なきところに繁栄なし

いかがでしょうか?
利益も取れず、良質なお客様も離れ、食品メーカーと良好な関係性が築けなくなる・・・;
こうなってしまっては手遅れです。
値下げ(値引き)は簡単。 誰でもいつでもできます。
その前に「なぜ売れないのか?」「何が足りないのか?」「どうすれば売れるのか?」を真剣に考えてみましょう。
そして、どんどん積極的に販促活動(プロモーション)を展開していってください。
最初から上手くいかないこともあると思います。
でも、安易に値下げばかりしているとその先に良い展開はありません。
知恵なきところに繁栄なし。
もがき苦しんで達成した先には明るい未来が待っています。
そして、それは大きな財産となって自分の中に残ります。
POP1枚からでいい。
まずは、できることからやっていきましょう。
千里の道も一歩から。
是非、チャレンジしてみてください。
応援しています。